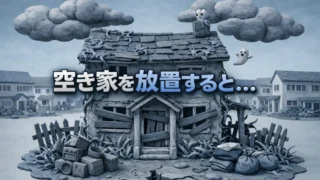「大きな〇〇はいらないね」叔母の言葉に深く頷いた 【不動産が負動産にならないように】

引越しも一段落したので、先日、相方の叔母さんのお宅にご挨拶に伺いました。
築30年以上経つ、落ち着いた二階建てのご自宅です。
その家は静かな住宅街に建っていました。
叔母さんの話では、最近は少しずつ古い家が取り壊され売りに出して、すぐに新しい家族が新築を建てて引っ越してきているそうです。
そんな街の変化の中、叔母さんがぽつりとつぶやいた一言が心に残りました。
「大きな家はいらなかったわね・・・。」
大きな家のなかで

お子さんたちが巣立ち、今では家の中もずいぶん静かになったといいます。
建てた当時は、未来の暮らしまでは考える余裕もなかったのだと思われます。
その家の広さは、今の生活には少し持て余すものになっているのかもしれません。
思い出が詰まった家ではあるけれど、掃除や、庭の手入れなども億劫になってきている様子でした。
売りに出せばすぐに買い手がつく立地でも、どこか踏ん切りがつかない様子。
先のことを考えてはいるものの、歳を重ねると「重い腰を上げる」というのは本当に難しいのだなと、お話を伺いながら感じました。
それでも、叔母さんとの会話はとても楽しく、美味しいお料理もたくさん振る舞っていただき、あっという間に時間が過ぎていきました。
帰り道で私たちの選択

その帰り道、相方と家の件について話をしました。
我が家には、子どもはいません。
そういうこともあり、今後も家を買うつもりはなく、ずっと賃貸で暮らしていく予定です。
もし、不動産を持とうとしたところで、その不動産を誰に託すのかも考えなければいけませんし、手続きも煩わしい。
だからこそ、家を持つことよりも、自由に動けることに価値を置く暮らしを選びました。
いざという時にすぐ引っ越せるように、今はお金をできるだけ貯めて、身軽に暮らしています。
老後に賃貸がかせてもらえないかも、と思ったこともありますが、その時はそのときになったら考えようと思っています。
相方も同じ考えで、そこはしっかり一致しています。
親族にも今後(退職後)どうするのか?とよく聞かれるので、そのままこの話をすると、少し驚かれます。
日本の持ち家率は50代で7割、60代だと8割とかなりの人が持ち家に住んでいるのが現状ですから驚くのは無理もありません。
でも、あえて私たちは家を持たない選択をして、老後を過ごすことに決めています。(未来のことは不確実でありますが)
そのように決めた理由も、今回のことだけでなく、昨年義父が亡くなり、気楽に考えていた親の家や土地の件で登記簿を取り寄せてみたら、思っていた以上に複雑だったことで、この件を何とか解決して、自分達は不動産を所有するのはやめようと思いました。
さいごに
「大きな家はいらなかったわね」
その一言は、軽く投げかけられたようでいて、とても重い言葉でした。
叔母さんの気持ちの奥には、きっとたくさんの経験と後悔と、それでも暮らしてきた時間の重みがあるのだと思います。
これから家を持とうとしている人にも、すでに家を持っている人にも、そして私たちのように持たない選択をする人にも、
それぞれの「ちょうどよさ」があるはずです。
自分たちの未来にとって、本当に必要な暮らしとは何か。
それを考えるきっかけをくれた叔母さんに、心から感謝しています。