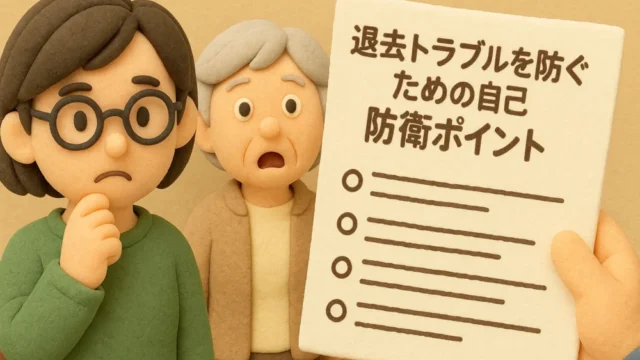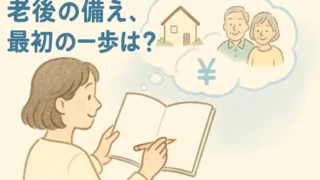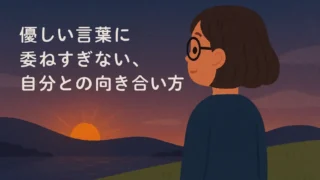その「優しい言葉」に、あなたはどれくらい心を委ねられますか?

「頑張らなくていいよ」「あなたはあなたのままで素敵だよ」「完璧を目指さなくて大丈夫」
こうした温かい言葉は、日々のプレッシャーや自己否定に疲れた心にとって、まさにオアシスのように感じられます。
誰かにそう言ってもらえた時、あるいは自分でそう唱えた時に、肩の荷が下りるような、フッと心が軽くなるような感覚を味わう方も、きっとたくさんいらっしゃるでしょう。
その瞬間の安堵や、自分を肯定されたような感覚は、疑いようのない、大切な癒やしの時間となり得ます。
私自身も、かつてこうした言葉に一時的な救いを感じた経験があります。その時は「これで大丈夫だ」と思えたのです。
しかし、もしその安堵が長続きしないとしたら?
その心地よい言葉の響きが消えた後、また同じように不安や自己否定の「思考グルグル」が頭の中を回り始めてしまうとしたら?
一時的な安堵は得られても、心の深い部分にあるパターンが変わらず、結局は元の場所に戻ってきてしまうように感じるのだとしたら、それは一体なぜなのでしょうか。
これは、「優しい言葉」そのものが悪いという話では決してありません。
問題は、その言葉が私たちの内面、特に「思考」とどのように結びつくかにあるのかもしれません。
思考が言葉を栄養にするということ

私たちの思考は、外部から、あるいは自分自身から与えられる言葉を、ある種の「栄養」として吸収し、そのパターンを強固にしていく側面があります。
もし、「頑張らなくていい」という言葉を、心のどこかで「どうせ自分には無理だから、努力しても無駄だ」という諦めや、健全な成長を拒む言い訳として無意識に受け止めてしまうとしたら、思考はその「諦め」「停滞」の方向へとエネルギーを注いでしまう可能性があります。
耳に心地よい言葉であっても、それが、今の自分にとって向き合うべき課題から目を逸らさせたり、内面の奥深くに耳を澄ませる機会を奪ったりするものであるなら、それは、知らず知らずのうちに思考の「グルグル」を強化してしまうケースも考えられるのです。
安易なポジティブ変換では解決しない
では、この「思考グルグル」から抜け出すにはどうすれば良いのでしょうか。
単に「ネガティブな言葉を、ポジティブな言葉に置き換えればいい」という話なのでしょうか?
もちろん、意識的にポジティブな言葉を使うことが、心の状態に良い影響を与えることはあります。
しかし、内側にくすぶる複雑な感情や長年の思考パターンを無視して、表面だけを無理やりポジティブに塗り替えようとしても、どこかに歪みが生じやすいものです。
それは、自分の正直な内側の声に蓋をすることにも繋がりかねません。
安易な言葉の置き換えだけでは届かない、心の領域があるのです。
思考を「観察」するというアプローチ
私がこの「思考グルグル」と向き合う中で重要だと感じ、そして希望を見出したのは、自分の思考そのものを「観察する」というアプローチでした。
たとえば、頭の中でどんな言葉がどんな感情と結びついて巡っているのか?
どんな時に、思考が特にグルグルしやすいのか?
そうしたことを、じっと見つめてみる。
そこにすぐ「良い」「悪い」と判断を下したり、何とか変えようと焦ったりする前に、まずはただ、「あ、今、自分はこんなことを考えているな」「思考がグルグルしてるな」と、一歩引いた視点から眺めてみるのです。
たとえば、日常会話の中でふと「今思ったんだけど……」と口にすることがありますよね。
この言葉は、自分でじっくり考えたというよりも、自然に思考が浮かび上がってきた瞬間に出てくるものです。
こうしたことからも分かるように、私たちの思考の多くは、意識的に生み出しているというより、むしろ「自然に浮かんでくるもの」であることが多いと感じます。
脳科学の研究でも、ぼんやりしているときに脳が自動的に思考を生み出している「デフォルト・モード・ネットワーク」という働きが明らかになっており、こうした思考に巻き込まれず観察することが、心の健康を支える一つの方法だとされています。
さらに、その思考に対して「これは良い」「これは悪い」と評価しているのも、また別の思考です。
だからこそ私は、そうした思考をすぐに意味づけしようとせず、「ただ浮かんでは消えていく流れ」として認識するようにしています。
こうして少し距離を置いて眺めるだけでも、思考に巻き込まれすぎず、心が落ち着く感覚が得られることがあります。
つまりこれは、良い・悪いを決めるのではなく、「今こういう考えが浮かんでいるな」という事実そのものを、静かに見届ける練習とも言えるのです。
この「観察」のプロセスを通して、あなたはやがて、自分自身の「思考パターン」や、「どんな時に思考がグルグルしやすくなるか」といった心の癖にも気づくようになるかもしれません。
そしてそこから、あなた自身に合った、「思考のグルグル」との付き合い方のヒントが、少しずつ見えてくるのです。
私が見つけた「集中」というヒント

私自身の体験から、興味深いことに気づきました。
特に何かをしているわけでもない「暇な時間」、ぼんやりしているだけなのに、頭の中ではいろいろな考えが次々と浮かび、時には同じことを何度も繰り返し考えてしまうのです。
このように、何もしていないように見える時間でも、脳は活発に働いていることがわかりました。
過去の出来事を思い出したり、これからやることを考えたり、心配事が頭をよぎったり…。
思考は静かに、しかし途切れずに動き続けているのです。
私が気づいた「思考がグルグルする」という感覚も、まさにこの脳の自然な働きの一部でした。
「あれもこれも」と思考が飛び交うマルチタスク
これとは異なる現象に、マルチタスクがあります。
たとえば、夕食を作りながら洗濯機を回し、子どもに話しかけられたことに答えつつ、頭の片隅で明日の予定を考えている…。
こうした複数の作業を同時に、または短時間に切り替えながら進める状態を指します。
しかし、人間の脳はマルチタスクに向いていないことが心理学や脳科学の研究でも分かっています。
たくさんのことを同時にこなそうとすると、それぞれへの集中が散漫になり、質が落ちたり、ミスが増えたり、結果として時間がかかってしまうのです。
さらに、マルチタスクを常態化させていると、頭の中を整理する力や、「今、本当に考えるべきこと」を見極める力が弱くなる傾向も指摘されています。
気づきから生まれた工夫:集中する時間を持つ
この気づきから、私は一つの工夫を始めました。
それは、「何か一つのことに意識を集中させる時間を持つこと」です。
これによって、思考のグルグルが入り込む余地を少しずつ減らすことができると考えるようになりました。
私にとって、この集中の対象は、
デール・カーネギーの『人を動かす』『道は開ける』をじっくりと読み込み、その内容を自分ならどう応用できるか考える時間であったり、資格試験の勉強に没頭する時間でした。
これらの活動は、私を一つのことに集中させ、思考の堂々巡りが入り込む隙間を自然に塞いでくれたのです。
これは、「思考を無理に止める」方法ではありません。
むしろ、自分の集中力を健全な方向へ意図的に活かすための、小さな工夫でした。
あなた自身の内面を探求する旅へ

「優しい言葉」は、疲れた心を癒やす大切なきっかけになります。
しかし、もしその効果が続かないと感じるなら、別の視点から自分自身を見つめ直す必要があるのかもしれません。
思考を否定したり、無理にポジティブにしようとしたりする前に、まずは「観察」すること。
あなたの思考がどんなパターンを持っているのか、どんな時に現れやすいのか、その仕組みに「おもしろいな」という好奇心を持って目を向けてみませんか?
そして、「何か一つのことに集中すると、思考は入り込みにくいらしいぞ?」といった、あなた自身に合った「工夫」や「過ごし方」を、日々の中で少しずつ見つけていってください。
こうした試行錯誤の積み重ねは、誰かから与えられた答えに頼るのではなく、あなた自身の体験と気づきを通して、自分らしい道を作っていくものです。
その過程の中で、考え方が整ったり、日々を落ち着いて過ごせる手ごたえを、少しずつ育んでいけるはずです。
きっと、今のあなたの中にも、まだ気づいていない工夫や可能性が隠れているはずです。
そして、あなた自身が積み重ねた経験や工夫は、同じように自分自身と向き合おうとしている誰かにとって、きっと力強いヒントになるでしょう。